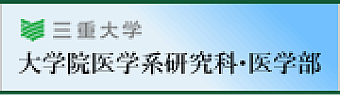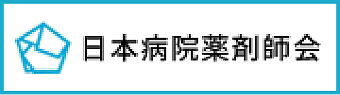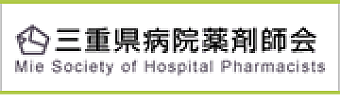ABOUT薬剤部概要
沿革
- 三重大学医学部附属病院薬剤部 トップ
- 薬剤部概要
- 沿革
| 年/月 | 事 項 | |
|---|---|---|
| 昭和18年 | 12月 | 三重県立医学専門学校設立、附属医院に薬局設置(津市栄町一丁目100番地) |
| 昭和22年 | 6月 | 三重県立医学専門学校附属医院から三重県立医科大学附属津医院となる |
| 昭和27年 | 2月 | 三重県立大学医学部が設置され医学部附属病院となる |
| 昭和39年 | 附属病院薬局を薬剤部に改組、外来調剤室、病棟調剤室、製剤室の3室を設置 | |
| 昭和42年 | 6月 | 病棟調剤室に三洋自動分包機導入 |
| 昭和43年 | 6月 | 外来調剤室にコニシ式自動分包機導入 |
| 昭和48年 | 5月 | 附属病院を新築移転(津市江戸橋二丁目174番地) |
| 同年 | 10月 | 附属病院が国立に移管され、三重大学医学部附属病院となる |
| 同年 | 12月 | 附属病院薬剤部を組織再編し、調剤室、薬品管理室、薬務室、医薬品情報室、製剤試験室、注射薬製造室、麻薬室の7室を設置(自動分割分包機、調剤用撹拌機、蒸留水製造装置、薬液滅菌装置等を設置) |
| 同年 | 5月 | 薬学生の薬剤業務実習受入れ開始 |
| 昭和51年 | 薬学生の薬剤業務実習受入れ開始 | |
| 昭和53年 | 4月 | 卒後の薬剤師実務研修受入れ開始 |
| 同年 | 7月 | 院外処方せんを発行開始 |
| 昭和56年 | 3月 | 附属病院に薬事委員会設置 |
| 同年 | 4月 | 注射薬処方せんに基づく個別調剤を開始 |
| 昭和58年 | 薬物血中濃度の測定を開始 | |
| 昭和61年 | 4月 | 薬剤部長が教授職になる(住田 克巳 氏着任) |
| 平成4年 | 5月 | 薬剤部第二代教授兼薬剤部長に 小島 康生 氏着任 入院処方オーダリングシステムを導入 |
| 同年 | 11月 | 薬剤部便りを月1回 発行 |
| 同年 | 12月 | 外来処方オーダリングシステムを導入 |
| 平成8年 | 2月 | 附属病院がエイズ治療拠点病院に指定される |
| 平成9年 | 9月 | 薬剤部に治験事務局を設置 |
| 平成10年 | 注射薬払出システム(松下電器産業社製)を導入 | |
| 平成13年 | 1月 | 院内措置により治験管理センターを設置 |
| 同年 | 注射薬個別調剤(一本渡し)を全病棟対象に拡大実施 | |
| 平成14年 | 6月 | 採用薬の一部を後発医薬品へ切替え開始 |
| 平成16年 | 4月 | 三重大学が独立法人化により国立大学法人三重大学となる |
| 同年 | 10月 | 薬剤部第三代教授兼薬剤部長に 奥田 真弘 氏着任 |
| 平成17年 | 1月 | 病院情報システムが全面更新(富士通製から日本IBM製へ) |
| 同年 | 1月 | 注射処方の全面オーダリング化、注射薬自動払出システム(アンプルピッカー)に連動 |
| 同年 | 4月 | 大学院医学系研究科が部局化される 薬品管理室にSPD導入(発注、検収、処置用薬の取り揃え業務を委託) |
| 同年 | 10月 | 副薬剤部長職(1名)が准教授職になる |
| 同年 | 11月 | 附属病院にオーダーメイド医療部設置(薬剤部は薬物血中濃度測定部門を構成) 附属病院に手術部サテライトファーマシー設置(薬剤師1名常駐) |
| 平成18年 | 1月 | 治験管理センターを臨床研究開発センターに改組(副センター長は薬剤部長指定職に) |
| 同年 | 3月 | 薬剤部ニュース(不定期情報提供紙)を発行開始 |
| 同年 | 4月 | 薬剤部研究室(臨床薬剤学分野)に大学院医学系研究科博士課程大学院生を初めて受入れ |
| 同年 | 6月 | 附属病院にがんセンター設置 薬剤部研究室が医学部講義棟1階・臨床研究棟2階から医学部臨床研究棟6階に移転 |
| 同年 | 9月 | 医薬品情報室ニュース(新規採用薬情報紙)を発行開始 |
| 同年 | 10月 | DI Weekly(添付文書改訂情報紙)を発行開始 |
| 平成19年 | 1月 | 附属病院が都道府県がん診療連携拠点病院に指定される |
| 同年 | 4月 | 附属病院に医薬品安全管理責任者を設置(薬剤部長が任命される) |
| 同年 | 2月 | 薬剤部研究室が医学部臨床研究棟6階から総合研究棟Ⅱ4階へ移転 |
| 同年 | 6月 | 「医薬品安全管理のための業務手順書」第1版発行 |
| 同年 | 7月 | 外来処方を全面院外発行(院外処方発行率約97%) 抗がん薬調製を全診療科対象に拡大 |
| 同年 | 10月 | 附属病院安全管理部に薬剤師ゼネラルリスクマネージャー(GRM)1名を配置 |
| 平成20年 | 1月 | 薬剤管理指導業務の対象を全入院患者に拡大 |
| 同年 | 4月 | 附属病院に化学療法レジメン審査委員会設置(委員長:薬剤部長指定職) 新生児集中治療室(NICU)での注射薬ミキシング開始 |
| 同年 | 6月 | 鈴鹿医療科学大学薬学部早期体験学習を実施開始 |
| 平成21年 | 4月 | 附属病院に外来化学療法部サテライトファーマシー設置(薬剤師2名常駐) |
| 同年 | 8月 | 日本TDM学会第30回セミナーを開催(医学部臨床第2講堂) 三重大学病院医療薬学研究会第1回例会を開催(医学部臨床第1講堂) |
| 同年 | 10月 | 薬剤部に助教1名(薬学教育担当)を配置 |
| 平成22年 | 2月 | 調剤部門支援システムを全面更新 麻薬管理システム導入 薬剤部研究室が総合研究棟Ⅱ4階から医学部探索医学研究棟2・3階へ移転 |
| 同年 | 4月 | 薬剤部組織を、薬務・薬品管理室、調剤室、麻薬室、注射薬供給管理室、総合製剤室、医薬品情報室、薬剤管理指導室、薬効評価解析室の8室に再編 |
| 同年 | 5月 | 薬学科生(6年制)の病院実務実習受入れ開始 |
| 同年 | 6月 | 附属病院に救命救急センター設置 HIV患者を対象とした薬剤師外来活動を開始 |
| 同年 | 12月 | 薬剤師による入院患者の持参薬チェックを全面実施 定時注射薬の交付時間帯を一本化 |
| 平成23年 | 8月 | 日本医療薬学会第32回公開シンポジウムを開催(医学部臨床第3講堂) |
| 平成24年 | 1月 | 薬剤部(セントラル、病棟サテライト、手術部サテライト)が新病院へ移転 病院情報システムが全面更新(日本IBM製,愛称:MINT) |
| 同年 | 2月 | ドクターヘリ用麻薬を救急外来に定数配置 |
| 同年 | 4月 | 注射薬処方箋の様式を全面変更 |
| 同年 | 7月 | ミコフェノール酸のTDMを開始 |
| 同年 | 8月 | 手術部サテライトファーマシーの薬剤師を2名に増員 |
| 同年 | 9月 | 救命救急センターサテライトファーマシー(専任1名)における薬剤業務を開始 |
| 平成25 | 2月 | APOTECA(TM)Chemoの臨床使用を開始 タクロリムス測定をディメンションからアーキテクトへ変更 |
| 同年 | 3月 | 平日の注射薬調剤・交付を施用単位に変更 Triple TOF5600システム(ABSciex社)を設置 |
| 同年 | 4月 | 薬剤部組織を4チームに再編 病棟担当者による定例ミーティングを開始 手術患者に対するアレルギー防止策を開始 |
| 同年 | 7月 | 病棟薬剤業務実施加算の算定を開始 |
| 同年 | 11月 | 日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部合同学術大会2013を開催(鈴鹿医療科学大学白子キャンパス) |
| 平成26 | 8月 | 医療安全・感染管理部にICT専任薬剤師1名を配置 |
| 同年 | 9月 | 第24回日本医療薬学会年会を開催(名古屋国際会議場) |
| 同年 | 10月 | 土日祝日の注射薬調剤・交付を施用単位に変更 |
| 平成27 | 1月 | アルベカシンとテイコプラニンの測定をTBA-25FR(東芝メディカルシステムズ)に移行 |
| 同年 | 5月 | 新外来棟開院 院外処方せんの様式変更(臨床検査値・化学療法レジメン名の印字を開始) 薬剤部薬剤管理指導室、外来化学療法部サテライトファーマシーが外来棟に移転 外来化学療法部での患者指導業務を開始 持参薬受付(仮設)設置 薬剤部外来患者窓口、投薬番号表示システム設置 |
| 同年 | 7月 | がん患者指導管理料3算定開始 |
| 同年 | 8月 | 薬剤部組織を再編 |
| 同年 | 10月 | 病院機能評価 3rdG:Ver1.0~ 一般病院2(500床以上)に認定 |
| 同年 | 12月 | がん薬物療法における薬薬連携研修会を開始 |
| 平成28 | 4月 | ファーマシーレジデント制度によるレジデント生の受入開始(1期生5名) 医療安全管理部に薬剤師を1名追加(2名体制) 注射剤の業務の一部にSPDを導入 |
| 同年 | 5月 | がん薬物療法に関するコミュニティ研修会「レジメンカフェ」開始 |
| 同年 | 3月 | 電子カルテ上での麻薬施用記録運用開始 病院玄関ホールに持参薬受付カウンターを設置 |
| 同年 | 10月 | 未承認新規医薬品・医療機器評価委員会における適応外使用・未承認薬使用の審議開始 |
| 同年 | 6月 | 「がん専門医療人材(がんプロフェッショナル)」養成プランとして「ライフステージ及びゲノム情報に応じた個別化利用を推進するがん専門薬剤師養成コース」「地域のがん薬物治療を支える薬剤師養成コース」を開設 |
| 同年 | 7月 | 病棟薬剤業務実施加算2の算定開始 |
| 同年 | 9月 | 第34回日本TDM学会・学術大会を開催(国立京都国際会館) |
| 同年 | 11月 | 日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部合同学術大会2017を開催(鈴鹿医療科学大学白子キャンパス) |
| 同年 | 12月 | 病院情報システム更新(日本IBM、MINT2) 内服薬処方せんの用量表記を変更(1回量、製剤量等) アルブミン製剤の交付業務を輸血部に移行 入院診療計画書における第三職種の記載(薬剤師など)を開始 |
| 平成29 | 2月 | 注射ラベルをRFID付ラベルに変更 |
| 平成30 | 6月 | 第21回日本医薬品情報学会総会・学術大会開催(鈴鹿医療科学大学白子キャンパス) |
| 平成31/令和元 | 4月 | 日本病院薬剤師会 妊婦・授乳婦専門薬剤師養成研修施設認定 |
| 同年 | 7月 | ピッキングサポートシステム(ポリムス)を使用した事務職員による計数調剤補助業務を開始 |
| 同年 | 12月 | 院内フォーミュラリー策定と運用開始 |
| 令和2 | 2月 | 総合サポートセンターへ1名(兼任)を配置 |
| 同年 | 5月 | フィブリノゲンHT製剤の交付業務を輸血部に移行 愛知県の薬系4大学も薬剤部実務実習生の受入を開始 |
| 同年 | 8月 | 薬剤部第四代教授・薬剤部長に 岩本 卓也 氏着任 |
| 同年 | 10月 | 教育研究分野の新設 臨床医学系講座 臨床薬剤学 Division of Clinical Medical Science, Department of Clinical Pharmaceutics |
| 同年 | 11月 | 副薬剤部長に向原 里佳 氏着任 |
| 同年 | 11月 | 最適使用推進GL該当医薬品等の使用届出制度運用開始 |
| 同年 | 12月 | 薬剤部講師に平井 利典 氏着任 |
| 令和3 | 1月 | 日本医療薬学 地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(基幹施設)認定 |
| 同年 | 2月 | 薬剤部准教授に加藤 秀雄 氏着任 |
| 同年 | 3月 | 日本臨床腫瘍薬学会 がん診療病院連携研修施設認定 災害備蓄薬の整備 |
| 同年 | 4月 | 日本医療薬学会地域薬学ケア専門薬剤師制度 研修生受入開始 |
| 同年 | 5月 | 医薬品トレーサビリティシステム(キュービックス)の導入 |
| 同年 | 11月 | 薬剤管理指導室の移転 持参薬管理室の設置 |
| 令和4年 | 2月 | CAR-T細胞療法(キムリア®)治療提供可能施設に認定 |
| 同年 | 3月 | 自動薬剤ピッキング装置 Drug Station(ドラッグステーション)導入 |
| 同年 | 4月 | 薬剤SPDによる手術部SP業務補助開始 |
| 同年 | 6月 | おんどとりを用いた薬剤部管理の薬用保冷庫・室内の温湿度集中監視を開始 |
| 同年 | 8月 | 『院外処方箋における事前合意に基づく調剤内容変更プロトコル』開始 個別化医薬品流通管理プラットフォーム「NOVUMN:ノヴァム」導入 |
| 同年 | 11月 | 注射抗がん薬の調製進捗状況確認システムを導入 |
| 同年 | 12月 | 『院内処方箋における事前合意に基づく調剤内容変更プロトコル』開始 |
| 令和5年 | 1月 | 薬剤師によるタスク・シフト/シェアの開始(処方仮登録、検査代行入力) |
| 同年 | 4月 | 電子処方箋の運用開始(院外処方箋) |
| 同年 | 4月 | 薬剤部に助教1名を配置 |
| 同年 | 4月 | 副薬剤部長に岡本 明大 氏着任 |
| 同年 | 8月 | 病棟薬剤業務実施加算2の算定病棟を拡大(総合集中、MFICU)、 周術期薬剤管理加算の算定開始 |
| 令和6年 | 1月 | 病院情報システム更新(日本IBM、MINT3) 調剤支援システムへ軟膏・水剤監査システム導入 |
| 同年 | 4月 | 薬剤部組織を、薬務・薬品管理室、調剤室、注射剤・製剤管理室、医薬品情報室、麻薬・手術部薬剤管理室、がん薬物療法管理室、病棟薬剤業務管理室、外来診療・TDM管理室の8室に再編 |
| 令和7年 | 3月 | 第14回日本薬剤師レジデントフォーラム開催(三重大学医学部臨床講義室) |
| 同年 | 3月 | 散薬調剤ロボット「mini Dimero」、一包化錠剤鑑査支援装置「Tab-sight S」、 次世代型薬剤識別システム「PROOFIT iQ」導入 |
| 同年 | 4月 | 薬剤師の勤務体制変更(管理当直から夜勤へ変更、4週8休制の導入) 休日を含めた全TPN調製の開始 |
| 同年 | 5月 | 薬物血中濃度測定業務を検査部へ移管 |